
ウクライナ・ザカルパッチャ州現地調査から −ルシン人問題に寄せて−
初夏の州都ウシュホロドは新緑に包まれ、訪れるものの胸を爽やかな印象で満たす。社会主義時代の無味乾燥な高層アパート群さえも整備された街路樹に覆われ、街全体が森の中にすっぽりと埋まっているかのようだ。街の中央を貫流するウシュ川沿いには戦後に植樹された桜並木が続く。この桜はsakuraという種だとウシュホロド市立第10学校(ハンガリー語教育併設校)校長アールパ・ペーテル氏が教えてくれた。sakuraは日本語で桜を意味すると、筆者が答えると、生物教師でもあるアールパ氏は丸い眼を更に丸くしてsakuraに見入った。散歩好きのウシュホロド市民にとって川沿いの並木道は格好の散歩道であり、晩春に咲き誇るsakuraは市民の自慢の種でもある。
スラブ研究センターでは昨年始まった二つの国際学術研究に加えて、今年度から新たに地方政治と農村経済に関する二つの国際学術研究が始まった。その概要については前々回のセンターニュースが伝えているが、今回、両班の代表研究者であるセンターの松里と筆者が第一回目の現地調査として、ウクライナのザカルパッチャ州を訪れた。筆者は地方政治の国際学術研究にも加わっているため、二重の調査目的をもって今回の調査を行い、とりわけザカルパッチャのハンガリー系少数民族の現状については、努めて多くの聞き取り調査を行った。というのは既にルーマニア、スロヴァキア、そしてユーゴスラヴィアのハンガリー系少数民族については日本でもしばしば紹介されているが、ウクライナ領のハンガリー系住民については全くと言ってよいほど実状が知られていないからである。今回の調査で、ウクライナのハンガリー系住民が一般に言われているほど無権利状態ではなく、むしろ独自のハンガリー語師範大学を持つなど、他所のハンガリー系少数民族の場合と比べて特権的な地位さえ築いていることがわかり、一週間という短い滞在ではあったが、貴重な調査結果が得られた。

|
| 戦略研究所 |
ザカルパッチャでの調査はもともと松里が昨年度に先鞭を付けた。彼の調査が縁で州政府と協力関係が生まれ、今回の調査とワークショップの開催が可能となった。とりわけ州教育局の高等教育担当局長補佐スヴェトラナ・イヴァノブナ・ミトリャエヴァ女史の貢献が大であった。同女史は局長補佐であると同時にウクライナ戦略研究所ザカルパッチャ支部の副所長でもある。副所長ではあるが、支部の招致では実質的な先導者の役割を果たした。今回のワークショップを戦略研究所で開催することを発案したのも同女史だった。公務員給与の遅配が問題となっているウクライナで、多額の予算を必要とする研究所の設置を、企画立案から立ち上げ(建物や機械設備をも含む)まで、一年もかけずに実現してしまう手腕は尋常でない。しかも戦略研究所ザカルパッチャ支部の創設記念に周辺諸国から専門家を招いて国際会議まで開催した。ザカルパッチャ州政治の詳細については近々松里氏が論文を発表するので、そちらを参照されたい。
以下では、この州の主な住民であるルシン人について、今回の調査で見聞したことなどを基に、少し述べようと思う。ルシン人はザカルパッチャ地域の中心的民族であるにもかかわらず、日本ではほとんど触れられることがなかったからである。この地域は旧ハンガリー王国の一部をなし、ハンガリー史専攻の筆者にとっても本来なら守備範囲に属するが、過去に一度センターの公開講座でルテニア問題を取り上げた時に触れたきりであった。また個人的にもこれまで一度もこの地を訪れる機会がなかったため、今回の調査は長年の念願を果たす好機となった。
ルシン人とは
ルシン人について考えるとき、そもそもルシン人なるものが存在するのか、あるいはルシンという呼称でよいのか、ここから問いを始めなければならない。今日のアメリカにおけるルシン学の薫陶であるP.R.マゴチ(Magocsi)によると、ルシン人は英語で表記するなら、Carpathian-Russia, Carpatho-Ukraine、Carpatho-Rusyn(ないしRusyn)、Carpatho-Ruthenia、あるいはSubcarpatian-Rusなどとなり、マゴチ自身はカルパチア・ルシン人(ないしルシン人)が適切だと考えている。もっともこれらの呼称はそれぞれ特定の時代意識や民族意識を反映したものである。最初の三つはロシア主義、ウクライナ主義、そしてルシン主義的な名称である。カルパチア・ルテニアとサブ・カルパチア・ルスは歴史的呼称であり、前者は第一次世界大戦までのハンガリー王国下のルテニア人を指し、後者は両大戦間期におけるこの地域のチェコ語表記ポト・カルパツカー・ルスの英訳である。ハンガリーでは歴史的にルテン人と呼んできたが、両大戦間を境にルシン人という呼称が使われ始め、今日ではルシン人が正式名称となっている。またルシン人はハンガリー・ルシン人の自称でもある。日本では第一次世界大戦までの時期についてはルテニア人、両大戦間期についてはカルパチア・ウクライナ人と呼ぶのが通例となっているようである。
このようにルシン人は多くの呼称を持つが、戦後の政治状況を反映させるならトランス・カルパチア・ウクライナ人となるかもしれない。つまり「カルパチアの向こうにいる(トランス・カルパチア)ウクライナ人」である。今のウクライナ政府はルシン人を別個の民族とは認めず、ルシン人問題は存在しないことになっているからである。これに対してルシン人の民族主義的急進派は、ルシン人は周囲のスラブ系民族とは異なる独自の民族であると主張している。
ルシン人の居住する範囲は、マゴチに従えば4つの地域からなる。1)現在のウクライナ領ザカルパッチャ州、2)南部ポーランドのレムコ地域、3)北東スロヴァキアのプレショフ地域、4)ユーゴスラヴィア北部のヴォイヴォディナ地域にあるルシン人村である。1)にはハンガリー領内のハンガリー化したユニエイトを含めることができるかもしれない。このようにルシン人はカルパチア山脈の北東湾曲部にまとまった居住圏を持ち、その居住圏はウクライナ、スロヴァキア、ポーランド、そしてハンガリーの四ヶ国にまたがっている。独自の国家を持たないルシン人は東欧のクルドと呼ばれることもある。ちなみに4)のヴォイヴォイディナのルシン人集落はハンガリー王国時代にカルパチア地区からの移住で形成されたようである。ただしヴォイヴォディナのルシン人は面として広がって住んでいるのではなく、幾つかのルシン人集落に集中している。ルシン人の総人口は1970年で85万と見積もられている。

|
| ウシュホロド市島の碑をバックに |
赤いルーシ
ルシン人の名称はルーシにさかのぼるという説もあるが、定かでない。19世紀まではルテニア人と呼ばれることが多かった。ではルテニアとは何か。森安達也氏によると(『東欧を知る辞典』)狭義には赤いルーシを意味し、広義には「かつてポーランドとリトアニアが領有した東方正教圏」となる。広義のルテニアは分かり易いが、赤いルーシは耳慣れない。白いルーシはベラルーシで馴染み深いが、赤いルーシとは何か。
1916年刊のレーヴァイ事典(ハンガリーで最も信頼されている事典)によると、言語的観点から次のように赤いルーシが定義される。すなわちまずロシア語が大ロシア語、小ロシア(ウクライナ)語、そして白ロシア語に分かれる。この場合のロシアは大ロシア主義的な意味合いで使われており、今日の定義からすれば、ルーシないし東スラブに相当すると考えられる。そして赤いルーシは小ロシア語の西部方言と見なされる。つまり「赤ロシア:ポドリエとヴォルヒニアの北部、ガリチア、ブコヴィナ、そしてハンガリー領内のルテニア人がこれに属する」と説明されるのである。ちなみにレーヴァイ事典が挙げる残りの小ロシア語の方言はウクライナ方言(南部小ロシア)と、ポレシエ方言(北部小ロシア)の二つである。
これで赤いルーシについて若干の言語的手がかりを得た。しかし具体的に他の小ロシア語方言とどこがどう違うのか、レーヴァイ事典は明かにしていない。小ロシア語としてのウクライナ語の特長はレーヴァイ事典によると、1)ロシア語のoやeはウクライナ語ではしばしばiにとって代わられる、2)強調のない母音もウクライナ語では曖昧化せずに発音される、3) ロシア語のiとyがウクライナ語では中間音になる、4)cは直前の子音の軟音化をもたらさない、5)gの音がhになる、6)呼格がある、7)未来形を表す動詞語尾imuがある、8)語幹末のh、ch、kが語尾変換に際してz、c、sに変化する、以上が具体例として挙げられている。さらに文語形成において、ロシア語では教会スラブ語が重要だったのに対して、ウクライナ語では口語から文語が発達したという大きな違いがあるという。ではこのウクライナ語一般の特長と赤いルーシ方言とはどう関係するのか、体系的なことはよく分からない。ウシュホロド大学のハンガリー研究センター所長でルシン系出身と言われるリゾネッツ教授によると、ルシン語はウクライナ語とロシア語の中間にあるという。読者諸氏のなかで赤いルーシ語についてご存じの方がいらっしゃったら、是非とも教えを乞いたい。
「文献はなくとも、現場がある。」これが地域研究者の強みである。卑近な例ではあるが、今回の調査から知り得たルシン語の一端を挙げてみよう。ザカルパッチャ州政府教育局少数民族教育課長ルドミラ・フルパ女史に面接調査した時のことである。おりしもその日は新しい州知事の誕生日だった。クチマ大統領による抜擢人事で、州第二の都市ムカーチェヴォの市長が州知事に赴任したばかりだった(ちなみに松里氏によると、このような知事の抜擢方法はまさにウクライナ的である)。筆者が午後四時過ぎに教育課の部屋に入ると、職員達に振る舞われたシャンペンで乾杯が始まるところだった。図らずも筆者は乾杯の環に加えられた。教育課にはハンガリー語を「父語」とするフルパ女史の他に、ルーマニア語を解する職員やスロヴァキア語を話す職員もいる。筆者は、「ウクライナ語ができなくて申し訳ない」と断って、片言のロシア語で「健康に na zdorovie」というと、その場に居合わせた職員から、ウクライナ語ではna zdorovja、ルシン語ではna zdravja、スロヴァキア語はna zdravieだ、と教えられた。瞬時に同じような言葉を次々に聞かされ、耳の出来が悪い筆者には何が違うのか明瞭に聞き取れなかった。確かに何か違いがあるように聞こえたが、「え、どこが違うの」という印象も強く残った。しかしその場でもう一度違いを聞き返すのは、なんともはばかられた。後日調べると、文字にして上に記したような相違があることが判明した。ちなみにポーランド語では na zdrowieとなる。
ルシン語には辞書がないので、図書館では何も分からない。そこでルシン語の表記方法はブダペストのルシン人少数民族首都自治委員会を訪ねた折りに、委員会議長のキシュ・ユディト女史に教えてもらった。ハンガリーでは1993年に少数民族法が成立し、13の少数民族に地方自治体レベルで民族自治組織が公式に認められた。ルシン人も13の公認少数民族の中に入っているが、ルシン語を話せるルシン系ハンガリー人の数は限られている。ちなみに13の公認少数民族とはロマ(ジプシー)、ドイツ系、スロヴァキア系、ルーマニア系、クロアチア系、セルビア系、スロヴェニア系、ポーランド系、ブルガリア系、ギリシャ系、アルメニア系、ウクライナ系、そしてルシン系である。
さて上述のキシュ女史はスロヴァキアのプレショフ地方出身のルシン人で、プレショフ方言のルシン語を話し、ハンガリー語とルシン語、さらにはスロヴァキア語のトリ・リンガルである。自らの国家をどこにももたないルシン人の場合、トリ・リンガルは珍しくない。キシュ女史の場合、姓がハンガリー風であり、ハンガリー語も外国人訛りなしに話すので、はた目にはハンガリー人としか見えない。ともあれ、彼女に「健康に」のスラブ語リストを見せると、一つ一つを順に口に出し、zd-o-r....のようにdとrの間にoが入るとロシア・ウクライナ的に響き、zdr....となってoが落ちると、もうこれは自分たちに親しく響く、という。筆者にとっては明瞭に聞き取れない違いだったが、スラブ系の人々にとっては親しく響いたり、あるいは異質に響いたりする訳である。語尾変化だけをみるなら、ルシン語はウクライナ語に近いようにも思われるが、ルシン人(ないしスロヴァキアのルシン人)自身は音の響きで西スラブに自らのアイデンティティを感じるのである。ただしよく考えると、これは卵と鶏の関係かもしれない。つまりルシン人が西スラブ人の間にまじって暮らしているうちに本来はあったかもしれないoが抜け落ちて、zdr...と発音するようになっただけなのかもしれないのである。いずれにせよキシュ女史の反応は興味深いものではあった。
赤いルーシに話を戻すと、ハンガリー・ルシン人少数民族全国委員会の幹部ポポヴィッチ・ペーテル氏から面白い話を聞いた。氏はザカルパッチャ出身でモスクワ大学卒業、ハンガリーに移住したという変わり種の地理学者であり、ブダペスト大学やブダペスト経済大学などで教鞭を執った経歴を持つ。現在は年金生活者の身だが、私設のルシン研究所を開設し、その所長を務めている。彼に赤いルーシとルシン人との関連について尋ねてみた。ポポヴィッチ氏の回答は次のようだった。ルシン人のルーツは「白いクロアチア人」であり、赤いルーシとは関係がない。そして赤いルーシは東スラブのうち南の方に住んでいた人々を指し、これは西に住んでいた白いルーシと対比される、というのである。まず興味深いのは、ルシン人の民族的起源を東スラブから切り離そうという姿勢である。確かにクロアチア人が今のクロアチアの地にたどり着く前、カルパチア山脈辺りにいたらしいことは、歴史書に書いてある。しかしクロアチアとルシンを繋ぐ具体的な証拠はなく、ポポヴィッチ説は今のところ純然たる仮説の域を出ない。
ポポヴィッチ氏の話で面白かった第二の点は赤いルーシの赤に関する解釈である。氏によれば、方角を色で示すという考え方がペルシャないし中国から伝わり、ベラルーシや赤いルーシ、ないし白いクロアチアの白や赤はそれぞれ方角を表し、白は西を示し、赤は南を意味するというのである。つまり白虎の白が西を、そして朱雀の朱が南を指すのと同じ語源であり、さらには東スラブのどこかに青龍や玄武もいるという話にもつながる。インタビュー時間の制約から、この話の典拠を聞きそびれてしまったが、新刊の「ポーランド・ウクライナ・バルト史」(山川出版)をひもとくと、中井和夫氏がポポヴィッチ説と全く同じ見解を取り、しかも色と方角の対応は中国起源であると言明している。さらに黒い(北)ルーシもあったという(いまのモスクワ周辺)。青い(東)ルーシについては不明のようだが、モスクワが玄武ということになる。そしてルーシの中心には黄金色のキプチャク・ハン国があったという。こうなると赤いルーシは「朱のルーシ」と書いたほうが似つかわしく思えてくる。センターの宇山氏の話では、ソ連時代からこの中国起源説は存在したが、しかしロシア人やベラルーシ人は心理的にこの説を認めたがらないとのことである。
ルテニア人とルテン人
赤いルーシが朱雀の朱と同じ起源であるという話に深入りしてしまったが、いずれにしても赤いルーシは他のルーシとともに東方教会経由でキリスト教を受容し、ギリシャ典礼を拝していた。しかし後にポーランド・リトアニア連合の支配が東に拡大し、1595年にブレストの合同がなると、赤いルーシも白いルーシと共にローマ教皇の権威を認めるユニエイト(合同派)教会を形成した。こうして先に指摘した広義のルテニア人概念が形成されたが、赤いルーシを意味するルテニアが白いルーシを含むこの地域の総称とされたのは興味深い。
何故ルテニア(赤いルーシ)が総称となったのかはわからない。しかしポーランド・リトアニアという東欧地域の勢力が東方に拡大したことにより、それまで東スラブの一部を指していただけの赤いルーシがルテニアという新たな呼称のもと、とにもかくにも非常に大きな地域を包み込むことになった。ここで問題が出てくる。つまりこの間にカルパチア山脈を越えてハンガリー王国領へと居住地を移した赤いルーシないし東スラブの正教徒が相当数存在していたのである。そもそも9世紀末にマジャール人がカルパチア山脈を越えてカルパチア盆地を征服したとき、ルーシの一部は現在のザカルパッチャに住んでいたという記録さえある。そして14世紀以降、ルーシ人は大量にカルパチア山脈を越えてハンガリー王国に移住し始めた。この他にも森林を生活の基盤とするルーシ人がカルパチア山脈の奥深くに数多くいたはずであり、かれらがカルパチア山脈のどちら側の世俗権に属していたのか、今となってはこれを正確に知ることは不可能である。

|
| 島の碑をバックに |
さて14世紀から移民としてカルパチアの尾根を越えてやってきたルーシ人は、ポーランド・リトアニア領内の正教徒と同様に教会合同の動きに巻き込まれた。いわゆる1648年のウングヴァール(現在のウシュホロド)の協定がそれであり、これによりハンガリー王国下のルーシ人正教徒もローマ教皇の権威を認めることになった。さらにトランシルヴァニアのルーマニア人正教徒も1698年と1700年の二回に分かれて、ユニエイト教会に加わる協定に調印した。
ここにいたってポーランド・リトアニア連合下のルテニア人との関係が複雑化する。まず従来の定義では、ポーランド・リトアニア連合下のユニエイトをルテニア人と考え、その中には赤いルーシだけでなく、白いルーシも含まれた。ルテニアは赤いルーシを意味するとしても、もはや「赤いルーシ」方言に基づく赤いルーシではなくなったのである。ところがこの時までに「赤いルーシ」の故地を離れてハンガリー王国に住みつくようになったルーシ人は、一方で西スラブ人やハンガリー人などと混じり合いながらも、ひとまとまりの集団を形成するようになっていた。このため彼らはブレストとは別にウングヴァールで教会合同に調印したのである。つまりルテニア人概念をポーランド・リトアニア連合の支配と結びつけるなら、ハンガリー・ルーシ・ユニエイトはルテニア人の範疇からはみ出すことになる。なぜならハンガリー・ルーシ人は広義のルテニア概念が成立する前にハンガリーに住みつき、ハンガリー王権と結びついてユニエイトとしての自己意識を形成したからである。しかしこれまでルテニア人とハンガリー・ルーシ・ユニエイトはほとんど区別されたことがなく、ハンガリーの歴史書でもルテニアを意味するルテンrutenがハンガリー・ルーシ・ユニエイトの総称として使われてきた。
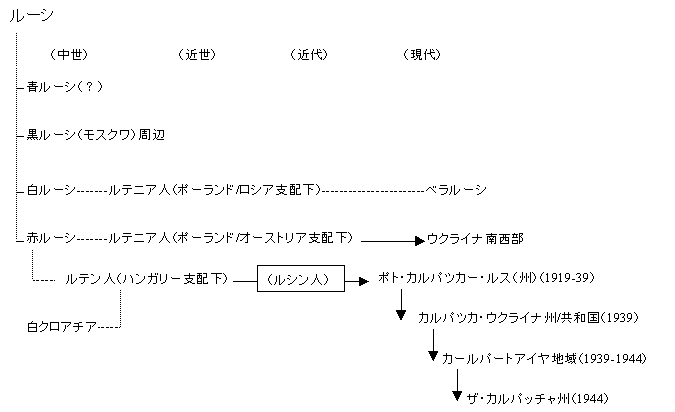
|
| ルシン人/ルシン人地域の時代的系譜 |
以上を総括すると次のようになる。ハンガリー・ルーシ人は「赤いルーシ」方言を通じて、カルパチア山脈の両裾にまたがる言語的共同体の一部を形成し、宗教的には正教徒としてキエフないしコンスタンチノープルに帰属した。その後、この人々はルテニア人と同様、歴史的な教会合同運動の落とし子として東スラブ・ユニエイトの一翼を担うことになり、呼称においてもルテニア人と呼ばれるようになった。しかしルテニア人と総称されたルシン人は近現代にいたって国家帰属が鋭く問われ始めた時、ポーランド・リトアニアのルテニア人とは全く異なる道を歩むことになった。以下では国家意識に焦点をあててルシン人への道を考える。
ルシン人へ
ルテン人は教会合同にいたる前から、世俗的にはハンガリーの世俗領主権に帰属し、国家的にはハンガリー王権の元にあった。しかし教会の帰属では、ハンガリーの国家宗教だったカトリック教会から独立し、ムンカーチ(現在のムカーチェヴォ)を司教座とする一つの教区を形成した。ハンガリーのカトリック教会は再三にわたって正教徒から教会税を徴収しようと試みたが、その試みはすべて失敗に終わった。正教徒達は十分の一税を村の教会に納め、村の教会はその大半を手元に残すことができた。このためハンガリーの東スラブ系正教会は非常に裕福で、村教会が数名の聖職者を抱えることも希でなかったという。このようにハンガリーの東スラブ系正教徒は聖俗別々の権威に属し、この二重性は彼らの社会経済的地位に好ましい結果をもたらした。
17世紀の教会合同は聖的な権威を東方からローマへと移し、ハンガリーにおける東スラブ正教徒の帰属意識を西方へと一元化させる契機となった。こうしてルテン人は教会合同を機にハンガリー王権と結びついたカトリック・ヒエラルキーの中に組み込まれたのである。しかしルテン人はムンカーチ教区の独立性を維持し、教会税についても独自の権限を保持したようである。この状態は今世紀にいたるまで、約3世紀間にわたって維持された。
他方、ポーランド・リトアニア連合の元に置かれた正教徒達(本来のルテニア人)は18世紀末の三度にわたるポーランド分割により、聖俗の帰属先が揺れ動いた。ロシア領となった地域ではユニエイト教会の解体が進められ、正教徒としてモスクワ主教座に帰依することが強制された。200年前の教会合同の運動が、今度は逆の方向で進行したのである。これに対してハプスブルクの支配下に入った地域(ガリチア地方とブコヴィナ地方)ではユニエイト教会が存続し、聖的な権威については帰属意識に変化が生じなかった。しかし世俗的な権威の中心はワルシャワからウィーンへと交代した。もっとも第一次世界大戦後、ポーランド国家が復活すると、ハプスブルク領だったガリチアとブコヴィナのルテニア人は再度ポーランド国家に帰属することになった。ところが第二次世界大戦の結果、この地域もソ連領ウクライナに編入され、ガリチアとブコヴィナのルテニア人は世俗的帰属においても教会的権威においても東方へと復帰することが求められた。こうして最終的にポーランドの主権から解き放なたれたルテニア人はもはやルテニア人でなくなり、ウクライナのユニエイトと呼ばれることになった。

|
| チェコスロヴァキア時代住宅 |
ルテン人はハンガリー王国時代にも二元的な聖俗の帰属意識や、ウングヴァール合同以後も維持された特権的な地位などを通して、ルテニア人とは異なる独自の国家帰属意識を形成した。またルテン人の間で1849年のロシア軍介入を機として親ロシア主義が高揚したが、1867年以降のブダペスト政府はこれに対抗すべく、マジャール化政策を強化した。もっともルテン人という呼称自体は先に指摘したとおり、ハンガリー国家への帰属意識と相反するものであり、ましてや独自のルテン人地域を指す名称でもなかった。この意味でチェコスロヴァキア時代のポト・カルパツカー・ルスはルテン人にとって、地域的一体性と国家的な帰属意識の双方を矛盾なく満たすはずのものであった。つまりポト・カルパツカー・ルスにおいてルシン人は赤いルーシやルテニアによっても、そしてハンガリー王国時代にも実現しえなかった自治を初めて政治日程にのせることができたのである。

|
| 州政府庁舎 |

|
| ハンガリー時代の旧市街 |

|
| ウシュ川左岸 新市街 |
東西の大国の狭間にあった東欧諸民族、その東欧諸民族の狭間にあったルシン人は言語的、宗教的、そして政治的にも独自の集団を形成することなく、複数の母集団に並列的に帰属する運命をたどった。従ってその帰属意識も複合的なものとなった。このようなルシン人の歴史を考えるとき、そこには東欧近代史全体が抱える問題群が集約的に表現されているといえる。と同時にここには地域の知恵ともいうべき共存への均衡感覚が培われてきたと思われる。ボスニアやコソボと同じ危機的な問題状況を常に抱えているにもかかわらず、それを地域内部の民族紛争や民族浄化へと至らせない共存の知恵である。何故紛争が起きなかったのか。これを問うことは、東欧で何故民族紛争が起こるのかを問うのと同じくらい重要なことである。
以上、ルシン人問題への糸口を歴史的な視点からさぐってきたが、この問題に迫るためには英露文献の他にウクライナ語、チェコ語、スロヴァキア語、そしてハンガリー語の文献にも通じること必要があり、研究者の共同作業が不可欠である。また今日的な問題としてウクライナ、ポーランド、スロヴァキア、ハンガリー、そしてルーマニアが国境を接するザカルパッチャ州をロシア・東欧の自由関税地域にしようという構想もある。東西合同の要ともいうべきルシン人地域を多面的・学際的に研究し、その成果を国際社会に問うことは、世界に対する日本の学術的貢献になるのではないか。