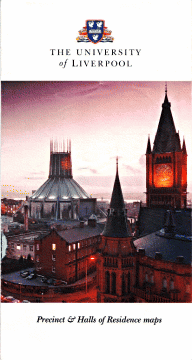
スラブ研究センターニュース 季刊 2002 年秋号 No. 91
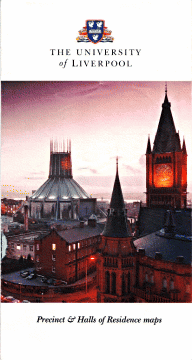 |
| リヴァプール大学キャンパス中央部: 中央の円形状建物は大学のシンボル、大聖堂 |
今回のイギリス滞在には研究上の目的が二つありました。 一つは平成 13 年度で終わる東欧農業改革関連の科研費の仕上げとして、英文で書いた論文を報告し、専門家達の批評を受けることです。 もう一つは平成 14 年度から始まる EU 東方拡大問題の科研費プロジェクトに関連して、イギリスの研究動向をつかみ、人脈を形成することです。 第一の目的については、この分野の第一人者、リヴァプール大学の N. スウェイン氏と議論する場を持つことが眼目でした。 事前に連絡を取り合っていたこともあり、リヴァプール大学の方で研究会が組織され、2002 年 1 月末に報告を行いました。 テーマがかなり専門的であったため出席者は限られていましたが、中身のある議論ができ、今後も研究協力していく確固とした基盤ができました。 また幸いにもスウェイン氏は来年度のスラ研客員外国人研究員として 10 ヵ月間札幌に滞在することになりましたので、共同研究が日本で推進されることになります。 スウェイン氏は東欧、ロシア、中国の比較研究を計画しており、国際的な連携研究がさらに一歩進むのではないかと、大いに期待しています。 関連する研究者の方々には改めて御連絡を差し上げるつもりでおりますが、その折りにはよろしくお力添えいただけますようお願い申し上げます。
第二の目的については、やや漠然とした計画しかなかったのですが、セント・アントニー校のヨーロッパ研究センターが EU と英国という総合題目でセミナーを開催し、結果的にこれで大いに助けられました。 もちろん東方拡大がセミナーの主たるテーマではなかったのですが、全体としてのイギリスの対 EU 政策、そしてイギリスの根強い統合懐疑論を目の当たりに実感することができ、いろいろと啓発されました。 しかもセミナーを通して英国外務省や EU 本部などの実務担当者とも顔見知りになることができ、人脈という点でも大きな収穫がありました。 参考までにこのセミナーのプログラムを掲げておきます。
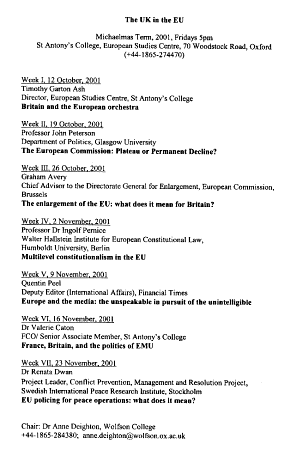 |
| セント・アントニー校ヨーロッパ研究センター・セミナー 「英国と EU」プログラム (クリックで拡大) |
前号でハイ・テーブルの効用について書きましたが、セント・アントニー校が果たしている国際的な研究拠点としての機能の根幹は、なんといっても、このセミナー形式で各研究センターが主催する連続研究会にあります。 学期ごとに 8 週間、毎週一回の研究会を通して特定テーマについてまとまった知識と人脈を獲得できるのです。 このような効率的かつ効果的なセミナーはオックスフォードという名声、そしてイギリス、しかもロンドンから 100 キロという地の利があって初めて可能なことです。 しかし、若干手前味噌の話になって恐縮ですが、今回のイギリス滞在ではスラ研の国際的役割を改めて実感したというのも事実です。 一つにはイギリスの専門家の間でスラ研の国際シンポジウムが学術的交流の場として高く認知されていることです。 しかしそれだけでなく、スラ研の国際シンポは、形式こそ全く異なるとはいえ、セント・アントニー校のセミナーに匹敵する、あるいは学問的にはそれを上回る国際研究拠点的役割を果たしているのだということを、今回のオックスフォード滞在で改めて認識させられたのです。
さて少し話は変わりますが、イギリスの EU 統合懐疑論に関連して、今回の滞在中、イギリス人の変わりゆくヨーロッパ観ないし自国観について考えさせられました。 一つのきっかけは数年前にノーマン・デーヴィスが著した大著『島々の歴史 The Isles: a History』です。 今もあちこちの書店で山積みにされています。 ただし 1300 頁もあるので、未だ拾い読みした程度にとどまっていますが、その前書きなどから察するところ、イギリス人はいま自らのアイデンティティ (自己定位) についてかなり深刻に揺れているようです。 つまりここに至ってついにイギリスは大英帝国の過去と最終的な決別を迫られているということです。 イギリスはヨーロッパではない、ロンドンからアジアは始まるというという皮肉な言い方もありますが、これまで長い間、イギリス人自身もヨーロッパ大陸とは異なる「英語圏」に自己定位の第一順位を与えてきたことは否定できません。 40 年前にチャーチルはベストセラーとなる英国通史『英語を話す人々の歴史 A History of English-Speaking Peoples』を著し、「統合ヨーロッパ機構の誕生を邪魔するつもりはないが」、と断りながらも、「ブリテン諸島 the British Isles およびイングランドから生や言葉や制度などを授かった諸国民」の統一的な歴史を書いたのです。 つまりイギリス史が世界史という立場です。 しかし今、N. デーヴィスはイギリス史を The Isles として地理的に限定しました。 ここに Britain という限定を付さなかったのは、アイルランドを依然として The Isles の歴史に含めたかったからであり、そこに僅かながら大英帝国的自己定位の痕跡を認めることができますが、歴史叙述の枠組みは根本的に変化しています。 そしてこの変化の背後には、イギリスのヨーロッパ「回帰」をめぐる自己定位の決定的変容があると思うのです。 40 年前、チャーチルは「統合ヨーロッパ」を脇に置くことができました。 しかしいまやイギリスはこれを避けて通ることはできないのです。 そんなことはもうとっくの既定事実であり、今さら何を、という御意見もあるかと思います。 確かにそうした現実を歴史学者が後追いしているという側面は否定できません。 しかし他方でイギリスの隅々にまで根を下ろしているアフリカ系、中国系、南アジア系の人々の存在を考えれば、単純にイギリスは植民地帝国からヨーロッパへ回帰したなどとは言えない現実があることも事実です。 こうした錯綜した現実の中で、いま「イギリス史の見直し」が行われているということです。
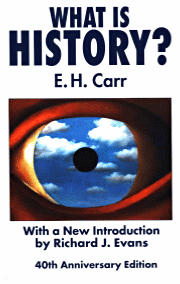 |
| E.H. カー著 『歴史とは何か』 (復刻版) 表扉 |
「イギリスにおける歴史の見直し」を感じたもうひとつのきっかけは、昨年の秋に E.H. カー著『歴史とは何か』の復刻版 (E.H. Carr, What Is History?, 2001, with a new introduction by Richard J. Evans. Palgrave 社からの復刻で、同社はイギリスの Macmillan Press 社がアメリカの St. Mary Press 社と合併してできた新会社) 出版記念をかねて、ケンブリッジ大学が大がかりなイギリス史再検討のシンポジウムをロンドン大学の歴史学研究所で開催したことです。 会議を通しての最大の主題はこれまでバラバラに行われてきた植民地史と「イギリス史」を総合する、ということだったと思います。 会議後にある長老格の参加者に「何故いま総合なのか」と、素朴な質問をしてみました。 答えは、「貴方は日本人か?日本人は歴史の理論化が好きなようだが、自分たちはそうではない。しかしいま植民地史を全体として振り返る時期に来ている」というものでした。 明らかにデーヴィスの問題作と一脈通ずるものがあります。
ところで、スラブ地域研究者としては、E.H. カー著『歴史とは何か』の復刻が気になるかもしれません。 しかもドイツに融和的だと評される『危機の二十年』も合わせて復刻されたのです。 予めお断りしておきますが、筆者はソヴェト・ロシア史についても、カーの業績についても専門家ではありません。 ですから以下に述べることにはとんでもない文脈的誤解があるかもしれません。 それを覚悟の上で、また皆様にお教えを乞いたいという意味で申し上げるのですが、今回の復刻は悩めるイギリス史学の反映と考えられるのです。 イギリスでカーといえば、もちろんソヴェト史の第一人者でありますが、それ以上に、まずは「歴史家」として読まれているようです。 つまり歴史学の「客観性」に異義を唱えたカーの代表作『歴史とは何か』はいまも歴史学徒の教科書的な存在であり、これまでに 25 万部以上が売れたロングセラーなのです。 そして今回、10 ポンドという手頃な値段でハードカバーの復刻版が出たことは、「歴史家」カー がいまも、そして今後も生き続けるであろうことの現実的証しと言えます。
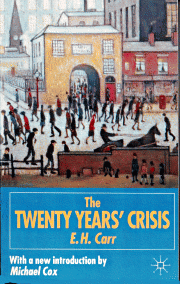 |
| E.H. カー著 『危機の二十年』 (復刻版) 表扉 |
ところがこの復刻版に長い序文を書いた R.J. エヴァンズは歴史家カーに対して極めて厳しい態度で臨んでいます。 もともとカーの客観性をめぐる論点については大論争があるのですが、今回のエヴァンズによる批判の中心はカーが依って立っていた歴史観に関するものです。 つまりカーの歴史観は勝者の歴史観である、というのです。 すなわち「カーは被統治者ではなく統治者に自己を同一化させ、敗者を歴史から排除している」とし、カーのエリート主義が非難されています (Introduction, p.37)。 「お役所人的」だという言い方をしている場合もあります (The two faces of E.H. Carr, www.ihrinfo.ac.uk/ihr/Focus/Whatishistory/evans10.html: 10.Oct. 2002)。 今回復刻されたもう一つの著作『危機の二十年 The Twenty Years' Crisis』(1939 年刊、こちらも興味深いことに、17 刷を数えたロングセラー) も勝者ドイツ、そして戦後のロシア論も勝者ソ連という「悪趣味なほどの勝者礼賛」 (Introduction, p.29) によって彩られているとさえ言い切ります。 エヴァンズは序文の最後で「以上のような欠点にも拘わらず本書は古典の地位を保っている」(同、p.40) と記し、申し訳程度に礼を尽くしていますが、40 頁に及ぶ序文全体はカー批判で終始しています。 このような序文を付して復刻された『歴史とは何か』が次の世代にどのように受け入れられてゆくのか、興味あるところです。 イギリスに限らず、ソ連崩壊後のロシアでは大著『ソヴェト・ロシア史』のロシア語版が「少し赤い」という理由で刊行中止になりました。 日本では「ユートピア社会主義者」として丸山真男に引き比べるカー評価もあります (渓内譲「E.H. カー氏のソヴィエト・ロシア史研究について」新版『ロシア革命論』へのあとがき、岩波現代文庫、2000 年、306 頁)。 カーについての多様な評価はいまだ尽きないようです (イギリス歴史学研究所の前掲ホームページに「歴史とは何か」をめぐる論戦が掲載されている)。 もちろん筆者には E.H. カー論を展開する能力は全くありません。 にもかかわらずここでカー批判をあえて取り上げたのは、エリート主義ないし勝者礼賛という視点でカーが批判されているからです。 つまりイギリス史の再検討という視点から見ると、ここで批判されているカーの歴史観は、そしてカーの経歴は、勝者であり続けた大英帝国の一部ではなかったかということです(註)。 ドイツへの融和政策、ソ連ないしスターリンとの同盟は紛れもなく大英帝国史の一部です。 これに対して今、世界史の主役であった時代がおわり、将来の歴史には自分たちの足跡が残らないかもしれない、あるいは単なる脇役でしかない「現代イギリス史」を生きている歴史家にとって、カーのような「勝者礼讃の歴史観」ではイギリス史はもはや描き得ないのではないでしょうか。 つまり今なされているカー批判の根底には、現在のイギリスが将来の歴史家によって「絶え間ない対話」を必要とされる「過去」たりうるのだろうか、という危機的な歴史的自己定位が横たわっているように思えてならないのです。
イギリスは歴史学の中で長い間甘やかされ続けてきました。 日本ではイギリス史は今も規範であり、模範です。 マルクスさえ!もイギリスのインド支配を肯定しました。 経済が悪くなれば、「イギリス病」という特殊な病名を与えられ、学問的な論争点にもされました。 ところがポンドを放棄し (欧州通貨同盟加盟)、国境を放棄し (シェンゲン条約加盟)、老後をポルトガルやスペインで暮らすために故国を放棄するようになった (住宅難とインフレの結末) 百年後のイギリスは、未来のイギリス史家達によって (いやその頃までにはイギリス史家という範疇は消滅し、EU 史家しか存在しないのかもしれませんが) 文字どおり EU の北にある島々 the isles (the Isles ではなく) としか呼ばれない存在になっているかもしれないのです。 EU に飲み込まれた「敗者」イギリスの姿です。
一般にイギリスが統一通貨を、そして EU 内の国境自由化を受け入れるのは時間の問題であると見られています。 しかし同時にイギリスで EU 懐疑論がそう簡単になくならないのは、歴史的な自己定位の危機が深く人々の心の中で広がっているからです。 この歴史的自己定位における危機意識はヨーロッパの反対側で、やはりいま EU 加盟と格闘している東欧諸国によっても共有されているのです。 ここで東欧の現状について立ち入ることはしませんが、ヨーロッパへの「回帰」と自己定位の間で揺れる欧州の諸地域、これが今年から始まった科研費研究「東欧の地域社会形成と拡大 EU の相互的影響に関する研究」の原点です。 ご興味をお持ちの皆様方からの御意見、更には今後予定されている研究会への御参加をお待ち申し上げております。
(註): 脱字により意味が反対に取られかねませんでしたので,訂正しました。 訂正箇所は「勝者であり続けた大英帝国の一部ではなかったかということです。」 「か」が脱落していました。 ご指摘いただいた塩川伸明さんに厚くお礼申し上げます。