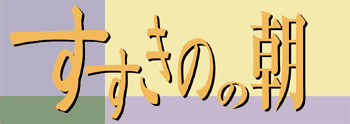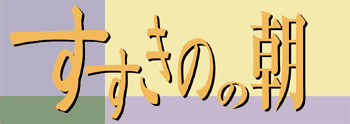道は裏通りへと通じていた。道幅はぐっと狭くなり、緩やかなカーブを描いて、奥のほうは視界から遮られている。一月も末の日曜日、SRCに短期滞在中のタイマーソフさんとフンドローヴァさんを連れて、札幌の街を案内した。お二人とも研究熱心な方で、平日は朝早くから夜遅くまで研究室に残って仕事をしておられる。休日に一度街の様子が見てみたいというお二人の要望にお応えして、
案内役を買って出た。とはいうものの、根っからの方向オンチで、しかもまだ当時は札幌に住み始めてから3ヶ月あまりしかたっていなかった僕は、周辺の地理について全くといっていいほど自信がなかった。それでも案内役を引き受けたのは、ただ看板の字を読んだり切符を買ったりするぐらいのお手伝いならできるだろうと踏んでのことである。
ちょうど雪祭りの準備が進む大通りで、雪像が作られる様子を眺めてから、狸小路へ。日本に来てから奥歯が痛み出し、歯医者からもらっていた痛み止めの薬も効力が切れてしまったタイマーソフさんのためにドラッグストアに立ち寄る。さらに100円ショップでは、ささやかな買い物に興じた。さて、これからどこに行こうか。たしか、地図ではこの南に大きな公園があったはずだ。南へ行こう、南へ。
もし僕が周辺の地理に通じていたら、表通りのもっと見映えのする道を選んで通ったに違いない。だが、僕のあやしい方向感覚だけを頼りに行動していた3人は、狭い裏通りに迷い込んでしまった。道の両側には、人目につかない裏通りの利点を生かした建物が立ち並んでいる。しかし、まだ朝の時間帯だったこともあって、辺りは不思議なほどのどかな空気に包まれていた。おじさんがせっせと雪かきをし、小鳥がさえずり、朝日がまぶしく雪を照らしている。きらびやかな外装を施した建物は、やはり人の目をひきつけるものらしい。タイマーソフさんがこの建物は何だと問うので、僕はただ「ホテルです」と、形容詞を省いて答えた。この際、仕方あるまい。
「その隣は?」

「それもホテルです。」
「では、あの向かいの建物は?」
「あれもホテル…。」
「一体サッポロには、どれだけ人が集まってくるんだ?」
「それは…。」
そのとき、フンドローヴァさんが才気煥発、僕に助け舟を出してくれた。
「あら、もうすぐ雪祭りが始まるじゃない。それに以前は、サッポロでオリンピックだってあったわ。」
自ら納得のいく説明を与えることができて、フンドローヴァさん、ご満悦の様子。それに対し、なおも釈然としないながらも、奥歯の疼きに気をとられて困惑気味のタイマーソフさん。「そうだ、そうだ」と頷きながら、内心ホッと胸をなでおろす僕。その3人の横を、まるで竜宮城の周りで魚が泳ぐように、夢見るような顔つきをした若いカップルを乗せた四輪駆動車がスイと走り抜けて行ったのに、両氏とも全く気づいていない様子だった。
* * *
彼らは何かを見落としたのだろうか? 注意深く観察しておれば気づいたはずの何かを見落としたために、彼らは僕が知っている事柄を知ることがないまま、
やり過ごさねばならなかったのだろうか?
ある知識を持つ者から持たない者への、知識の伝達という経路を介してのみ、人の認識が形作られるのだとしたら、おそらく彼らは永遠に浮かばれることがないだろう。知識を持たない者は、知識を持つ者の意向に全面的に依存せざるをえない。
両者の関係は、状況が変われば立場も変わる。3月末のある夕刻、僕はクリミア半島の中心、シンフェローポリ市の街を流れるサンギラ川のほとりを歩いていた。献身的に僕の面倒を見てくれるセルゲイが、ぽっかり空いた日没前の時間に、家の周りを散歩がてら案内しようと誘ってくれた。川幅はせいぜい5、6メートルほどで、両脇には遊歩道に沿って柳やプラタナスの木が植えられている。ちょうど桜の花が咲き始めるシーズンで、二人は心地よい春の風に吹かれて歩いていた。と、セルゲイが「何か気づかないか」と僕に尋ねる。僕は感想を訊かれているのかと思って、とてもきれいな眺めですがすがしいというようなことを言ったら、彼は僕を制してこう言った。
「よく見てみろよ。ここには柵がないだろう?」
後ろを振り返ってみると、なるほど、遊歩道と川の間に続いていた黒い鉄柵が、途中で途切れてなくなっている。その途切れたところからは、ただ足元にコンクリート製の土台だけが点々と行儀よく並んでいる。セルゲイの話によると、誰かが屑鉄として売るために、夜中に来てひそかに持ち去ったのだそうだ。それにしても、見たところ柵は大人二人でようやく動かせるくらいの、かなり重厚なつくりである。これを盗んだ人はよほど生活に困っているのかなあと僕がつぶやくと、彼はいきりたって、断固とした口調でそれを否定した。
「とんでもない! 生活が苦しいからといって、こんなことをするやつはいない。やつらには自分の頭で考える習慣がないんだ。自分の手で働いて、お金を稼ごうという考えを持ってないだけさ!」
* * *
もしあの時、セルゲイが話を持ち出さなかったら、僕は完全に鉄柵のことなど見落としていただろう。そして、実際に生じている社会問題にせよ、セルゲイがもっている個人的な信条にせよ、結局知らずに終わっただろう。翻ってみるならば、すすきのでは、僕は自分の知っていることを彼らに話さなかった。それを話すのは都合が悪く、全部説明する必要はないと思ったからである。セルゲイは僕に、彼の知っている都合の悪いことを、あえて話してくれた。経済的な窮状を訴えるためではなく、仕事に関する自らの信念を表明するために。知識の伝達ということに関していうならば、この二つの例が示すように、ある知識を獲得することができるかどうかは、すでにそれを持つ者の意向に全面的にかかっている。人は、それを望む場合にはすすんで知識を提供するが、反対にそれを望まない場合、都合の悪いことの前で口をつぐみ、ペンを止めてしまう。どんなに悔しがってみたところで、これはどうすることもできないだろう。
だが、人が何かを認識するのに必要なのは、外から得られる知識だけに限られるだろうか? その知識がかえって、他のルートをたどって得られる情報や、感覚的なものを遮断してしまうことがあるのではないか? すすきので僕が二人に街を案内したとき、目に映るものに驚きをもって実感していたのは彼らであり、
苦笑いしながら目をそらしていたのは、僕のほうではなかったか? その間にも、彼らはもっと実感として、建物の屋根の形や壁の材質・色、看板の文字(たとえそれが理解できないにしても)などを、生き生きと感じ取っていたかもしれないのだ。
幸いなことに、彼らとともに歩いたことで、僕自身の見方にもすでに変化が起こり始めている。固定的なイメージをもって思い浮かべていた裏町とはおよそ不釣合いな光景
—— 雪かきをするおじさん、小鳥のさえずり、輝く朝の日差し —— に出っくわした。僕の認識においても、すすきのの朝は生活者の新しい一日が明けるのを待ち受けている。