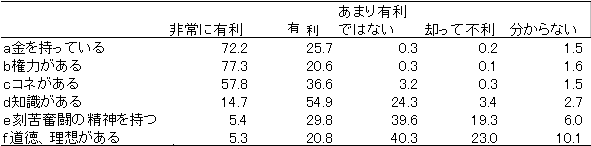
中国:社会意識の“転型”
菱 田 雅 晴(静岡県立大学国際関係学部)
制限速度を遥かに超えてスポーツカーが疾走する高速公路の脇の農道を、馬車に野菜を満載した農民がゆったりと進む。大都市の目抜き通りで出会う小姐たちも、六本木、青山と見紛うばかりのその艶やかな姿のみに眼を奪われてはならない。その彼女らとて、貴州の農村から昨年上京したばかりかも知れないのだ。
こうしたスナップショットのみからではないにせよ、一様たるべき時間の流れが、現代中国では、加速度的に速くなっているようにも見受けられる。1978年の改革・開放プログラムへの着手以来の経済、社会の急激な変化がしばしば観察されているが、90年代を迎え、その変化そのものが慣性(inertia)を強め、変化速度自体に一層の弾みがついたようにも思われるからである。のみならず、中国全体の時間の流れ自体にも歪があり、それらの地域的、階層的"時差"ともいうべきものがヨリ拡大しつつあるようにも思われる。
いうまでもなく、その最大の背景は、中国経済の市場化の進展、それに付随する国際化の浸透ではあるが、その市場化、国際化のうねりも90年代入り後、加速度的な展開を見せ、世界の中での中国の重みが一層増してきている。国際社会にあって、中国をも含めた“G9”の可能性が舞台裏では喧伝されるまでに大きな関心と注目が寄せられる中国のプレゼンスの高まりは、現代中国に生きる人々に、未曾有の民族的自負心と高揚感を与えているのではなかろうか。その一方で、上述の"時差"拡大による中国社会内部の原子化現象とも呼ぶべき分岐と多極化が発生しつつある。逆に謂えば、それらこそが、変貌する中国社会にヨリ急速な変貌テンポを加えている当の要因といえるかも知れない。
さて、「体制変容の政治社会学」と題された本ラウンド・テーブルは、スラブ・ユーラシアの変動と現代中華世界の構造変動をテーマとする両重点領域研究のそれぞれの知見を持ち寄る「知的総合」作業を通じて、それぞれの研究課題の進展に資する何らかを見出そうとする試みと解される。本報告に与えられたテーマは、現代中国の変貌著しい社会領域における問題相を剔抉し、ラウンド・テーブルにおける議論の素材を提供することではあるが、紙幅の制限もあり、ここでは現代中国における社会意識の存在様態を瞥見することとしたい。
というのも、ある社会の変化を採り上げる場合、ミクロレベルとしての諸個人の行動様式の変化から、マクロの社会体系、社会構造の変化に至るまで、はたまた、制度、政策といった社会のいわば"固い"部分の変化から、人々の内面としての意識の動向を見ようとするものまで、さまざまなレベルを設定することができるが、前者の行為レベルの変化は比較的見易く、世相の変貌として数多く語られている。ここでは、制度の変化と行為レベルの変化をとり結ぶ、いわばブラックボックス的存在="見えないもの"としての社会的意識の変化を、中国側サンプル調査等のデータに依拠して、簡便に跡付けることで、その任を果たしたい。
結論先取り的に述べておけば、かつて、毛沢東時代の中国が、高い精神性に溢れた、公的論理が覆う社会として描かれることが多かったのに対し、改革開放の新たな段階を迎えつつある現時点にあっては、全く対照的な位置つけが可能ともいえる。現代中国に生きる人々の社会意識に関して、現世主義的色彩の濃い物質的社会観としての過度の拝金主義ないし拝権主義の傾向、そして私的領域への逃避傾向を、その特徴として挙げることが出来る*1。
先ずは、中国側における公式的な自己認識像を確認するところから始めよう。「体制変容」という本ラウンド・テーブルのキーワードに対し、中国にあってほぼ同趣の目的で使われるのが“社会転型”なる概念であり、社会領域の諸問題を取り扱う中国側論稿にあっては、しばしば自明の枕言葉として用いられてさえいる。
例えば、中国社会科学院の“中国社会発展研究”課題組は、そうした自己認識作業の最も代表的なものと思われるが、同執筆グループは、現代中国における社会発展過程の“中国的特色”として、現代中国が今世紀における最も深刻な“転型”時期にあり、その“転型”が二つの“転変”から構成されていることを、自らの分析フレームワークの前提として掲げている*2。すなわち、「高度に集中された計画再分配経済体制から社会主義市場経済体制への転軌」としての「体制転軌(Institutional Transition)」と「結構的転変(Structural Transformation)」の両者である。後者の「構造転変」は、「農業・郷村そして閉鎖性から成る伝統社会」から、「工業・都市そして開放性を特性とする現代社会」への“転型”とされる。これら両者が78年以来の改革の現実的進展過程にあって渾然一体化、同時進行しつつあることを指摘しているが、“中国社会発展研究”課題組は両者間の相異なる性格をヨリ強調するところに力点を置いている。この点こそが、旧ソ連、東欧諸国の「体制変容」およびNIEs諸国等の社会変化等との差異を際立たせる中国的特色だとも指摘する。
鄭杭生らの中国人民大学グループも、中国社会が伝統型社会から現代型社会への急速な“転型”過程下にあるとの指摘*3を行っている点ではほぼ同趣である。鄭杭生らは、更に、中国社会の“転型”過程を、アヘン戦争以来、第一段階(1840-1949年)、第二段階(1949-1978年)、第三段階(1978年以降)と時期区分し、第三段階としての現在を“社会転型”の加速期として、・速度(発展速度と社会的受容力)、・広度(用具的・制度的側面に限定されるものか、それとも全面的か)、・深度(身分、社会的地位、価値観等社会生活の深層部にまで至るものであるのか)、・難度(利害関係の調整)、・向度(モデル選択)等の5つの側面で、前2者の時期とは相異なる特性を有するものとして描き出そうとしている。
これらの中国的議論の構造は、「体制変容」あるいは社会主義の相対化という側面を可能な限り括弧に入れ、歴史のヨリ大きな広袤において捉え返そうとするところに特徴を見出すことも出来る。しばしば政策文書に登場する、「改革」=制度変革と「発展」=生産力の拡大という対概念と同根とも思われる。とりわけ、鄭杭生らの中国人民大学グループには、第二段階=社会主義期を、1840年以来の歴史の連続性の裡に相対化しようとの方向性も特徴的に看取されるが、事実としての「体制変容」の大衝撃を「構造転変」の裡に吸収させようとの政治的な意図が先行しているのかも知れない。
これらのいわば上からの入念な“転型”概念の設定にも関わらず、現代中国に生きる人々を直接対象とした意識調査ではヨリあらわな姿が浮かび上がって来る。
北京社会心理研究所の行った社会意識調査に依れば、当今の中国人の社会意識として極めて驚愕すべき結果が現われている*4(第1表,N=2600)。「現在の社会でどのような人が有利か」との設問に対し、「金を持っている人」が「有利だ」と回答したのが、調査対象としての北京市民中の97.9%(「非常に有利」72.2%、「有利」25.7%)と圧倒的大多数に上っている。同様に、「権力を握っている人」および「(権力と)関係=コネを持つ人」が有利だとの回答も、それぞれ97.9%(「非常に有利」77.3%、「有利」20.6%)および94.4%(「非常に有利」57.8%、「有利」36.6%)と圧倒的な数値に達している。まさしく、現代中国社会では、(少なくとも本調査の対象としての首都、北京に見られるような中国における「先進地域」にあっては)「ゼニを持つ者、権力を握る者がハバを利かせている」との一般的認識が浸透していると見てよい。
その一方で、知識、刻苦奮闘精神あるいは道徳・理想といった精神的価値に対する評価は異常なまでに低い。先の調査では、「知識のある人」が現代中国社会で有利だと答えているのはわずか14.7%に過ぎず、ましてや「刻苦奮闘精神のある人」、「道徳、理想の持ち主」にいたっては、それが有利だと考えるのは、5%台にとどまり、逆に、不利だ」との認識がそれぞれ58.6%、63.8%にも上っている。
先ずはその赤裸々な現世主義の吐露にややたじろぎを禁じ得ないが、もし、同趣の調査が70年代初頭ないし60年代に行われたならば*5、恐らく公式には「道徳、理想を有する人々」という建て前に属する回答が絶対多数を占めるであろうし、何らかの方法により、本音部分の回答が得られたとしても、「党員」「権力に近い人々」といった回答が圧倒的となるかも知れない。ある意味では、こうした調査から、逆に、改革期を迎えてようやく中国市民も自らの真情を吐露する機会を得たともいえる。
第1表 誰が有利か(百分比)
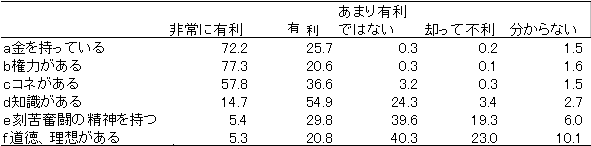
出所:馮伯麟「市場経済条件下的社会心態研究」『社会学研究』1995年第2期
何れにせよ、現代中国に生きる人々の眼に映ぜられた社会像とは、物質的富こそが最大の価値であり、それを実現するものとして、富そのものと権力があり、"銭(qian)"と"権(quan)"こそが世渡りの最高手段であり、徳ないし理想といった精神的価値は重荷でしかないという現世主義的色彩の濃い物質的社会観に外ならない。
それにもまして、ここで注目されるのは、「富が富を生む」という認識である。従来、イデオロギーとしての社会主義が公的世界を覆い尽くす中にあって、禁欲を強いられてきたことから、物質的富そのものへの躊躇の念もあったものの、改革初期80年代までは、商才、小才さえあれば、富を獲得し得るとの楽観が存在した。それこそが後述「先富論」により導かれた“中国夢(China Dream)”であり、事実幾多の成功事例を生み出して来た。にも関わらず、この93年時点の北京調査にあっては、富を生むものとして、富そのものが権力とともに挙げられている点は特筆に値する。かつての「額に汗さえすれば」との成功への楽観論--“中国夢”は姿を消しており、裏返せば、「富なくしては富が得られない」との悲観的認識が拡がっていることになる。「権力のある者ほど富む」ないしは「富める者ほどヨリ富む」という形での、格差-- とりわけ出発点としての格差への認識がこのレベルに達しているとするならば、その帰着としての自信喪失と虚無主義を、大衆サイドの社会意識の底流に見出すことも許されよう。
翻って、かくして富に至る手段的要素が限定される中にあって、80年代後半以降急速に浮上してきたものとして、腐敗現象を捉えることができる。ここにいう腐敗とは、単なる行政失陥(maladministration)等の逆機能現象あるいは「腐敗した一部個人」の行為のみならず、「向銭看」(=利害得失を判断の基礎とする)に「一切」を冠した、すべての判断を利害関係のみに基づくという「一切向銭看」なる、ほぼ現代中国社会全体にあって共有される価値意識の現実相への転化に外ならない。
当然、腐敗に関する市民の関心には極めて高いものがあり、各種輿論調査の結果を俟つまでもなく、常に関心事のほぼトップに挙げられている。腐敗の程度に関して、ある大規模サンプル調査(N=7000)では、89.3%が「今日の腐敗現象は(極めて)深刻」と看做している*6。無論、当局側にもこれに対する「体制危機」認識は黙示的にせよ存在するものの、具体的な政策措置は、「腐敗した一部分子」に対象を局限した法執行の厳格化に限定されざるを得ないところから、政府による腐敗反対キャンペーンの効果に期待を寄せるのはわずか14.6%に過ぎない*7。また、華中師範大学社会心理研究所の武漢市民1000名に対する腐敗意識調査では、85.9%の市民が腐敗現象の増加と「改革開放政策への着手」を関連させているが、54.6%が「腐敗は根絶されることはありえない」との悲観的見方を掲げている*8。
しかしながら、ここで最も問題とされるのは、いわば「腐敗の共犯関係」ともいうべき広がりであろう。上記の「一切向銭看」意識の官僚層への反映こそが受託収賄とされる行為であり、逆に「商」サイドから「スピード・マネー」(G・ミュルダール)としてビジネスの“効率化”に向けられたのが贈賄行為である。まさしく贈収賄実施の機会に恵まれるか否か、この一点こそが、現実の腐敗行為を行うか否かのわずかな分水嶺でしかない。
その意味では、中国青少年研究センターが実施した「賄賂が焦眉の急の問題の解決に役立つならば、賄賂を行うか」との問いに対する回答は、こうした腐敗の共犯関係を雄弁に物語っている。すなわち、回答者のうち、決然と「行わない」と答えたのはわずか24.7%に過ぎず、「行う」あるいは「状況次第」との回答が53.6%に上り、21.6%が「何ともいえない」と明確な回答を留保している*9。更に、先の華中師範大学調査では、「社運を賭けたプロジェクトで実力者に賄賂を贈らねばならなくなった。あなたはどうしますか」との設問を掲げているが、その回答は、「警察に通報する」が16.3%であるのに対し、過半数の53.7%が「賄賂を贈る」であった。
当局側の反腐敗キャンペーンに描かれた「極々一部の腐敗分子」なる定式化は現実的説得力を持たず、社会意識で断ずる限りは、寧ろ4人のうち3人までが「腐敗分子」である。ヨリ大きな腐敗行為には糾弾の声を挙げ、同時に自らもその腐敗予備軍たることに何らの躊躇を示さないというアンビヴァレントな社会意識の様態がそこには観察される。「一切向銭看」の完成態であり、「腐敗糾弾」の声も実際のところ腐敗機会の不平等(!)を訴える「嫉妬」のレベルにとどまっていることになる。
一方で、かつて文革期に強調された筈の「政治的自覚」、「政治的人間」像は、最早その片鱗も見られない。前記の北京社会心理研究所調査では、そうした政治的関心を測定するべく、テレビ、ラジオ、新聞等マス・メディアの報道内容に対する関心の度合をサーベイしているが、そこにもアパシー(apathy=政治的無関心)の高まりが顕著である。メディアの報道内容のうち「最も関心のあるもの」として一項目選択回答(複数選択を許さず)されたのは、社会ニュース(28.3%)、政治報道(26.4%)、経済ニュース(17.6%)の順であった。政治ニュースへの関心が依然高いようにも見受けられるものの、(わずか)3年前の同調査では、政治報道が最主要関心との回答が40.7%と圧倒的であったことからすれば、1990年代を迎えてからの政治的関心の急速な低下は否めないところとなっている。因みに、同調査時点で行われていた北京市の各区県レベルの人民代表選挙への関心度を尋ねたところ、「関心なし」が52.4%を占め、また、投票行動についても49%が「適当につきあう」、「時間を無駄にしたくない」と極めて率直なまでに否定的であった*10。
この関連では、政治への有効参加感の低下が、それを裏付ける背景となっている。「政治的決定に対し、何らの影響力も持たない」という意見に対して、49.8%が同意しており、「政治とは複雑怪奇にしてわれわれ庶民の理解を超える」という見方には49.2%が同意を示している*11。
そもそもこうした社会意識の変化とは、プレ改革開放期としての毛沢東時期における社会主義への幻滅に端を発するものとの仮説を設定することができる。中国の場合、建国直後、人々が世界の中で自らを定位し、判断、認識の基準とするいわば世界了解の座標軸たる「準拠枠(frame of reference)」として選択、設定したものこそが「社会主義」であった。
ただ、「社会主義」とはいっても、多くの人々がイデオロギーとしての社会主義を完全に理解し、理論的かつ悟性的な認識の結果として選択するべくもなく、そうしたルートからの社会主義選択は寧ろ極々少数にとどまり、大衆にとっての「社会主義」とは、「汚辱に満ちた中国の命運」を覆す手段として、ナショナリズムとほぼ同根のものであった。更に言えば、大多数の人々の率直なところは、建国=国家統一による混乱情況の収拾、制度建設による日々の生活向上という眼に見えた成果-- 日常的向上感覚こそが、「社会主義」の直接意味するところであった。
これに、「不患寡而患不均」(=貧しきを憂えずして、等しからざるを憂う)という中国社会に伝統的に存在していた平等希求が親和的に作用することにより、「準拠枠」として選択された社会主義は、中国社会を席捲し、「建国の情熱」(Revolution Zeal)ともいうべき熱情が新中国を覆った。
だが、その「建国の情熱」も、「大躍進」「プロ文革」といった激動の中国現代史の展開と共に、急速に減衰する。上述の大衆の「社会主義」理解が、日々の生活向上期待感というレベルにあったればこそ、その期待度に比して十分な向上感覚が得られないところでは、幻滅感が進行し、大衆運動形態による悲惨な結末とも相俟って、「社会主義」への懐疑は必然でもあった。その限りでいえば、改革開放着手以前の段階で、既に大衆レベルでは、「社会主義」は、「準拠枠」としての本来の機能を失効させていたものと思われる。
人々は、「準拠枠」の喪失感から、いわば「神なき世界」に身を委ねていたことになるが、そうした状況にあって、再び《神》が与えられることとなった。それこそが、 小平氏の呼びかけによる「先富論」であり、それにより導かれた経済改革のスタートであった。
周知の通り、「先富論」とは「条件のある個人、企業、地域が刻苦奮闘により先に豊かになることを、全体富裕を目標とする中国の経済政策の中で認めようではないか」との 小平氏の周到な定式化ではあるものの、実践的には、民にとって、お上からの「金儲けの勧め」と映ぜられることとなる。かつてのイデオロギー的な糾弾を惧れることなく邁進し得るマネービルディングへの途が、「神なき世界」の人々に圧倒的な説得力をもって提示された。新たな「準拠枠」としてカネが選択されたことになる。先の「建国の情熱」にも似て、いわば「改革の情熱」(Reform Zeal)が急速に改革期中国を覆う熱情となり、それこそが改革を推進する社会心理的ブースターエンジンの役割を果たすこととなった。しかし、急速に浸透したその「改革の情熱」も急速な減衰過程を辿るのは、先の「建国の情熱」とほぼ軌を一にしており、まさに歴史の皮肉な反復である。
と言うのも、第一に、先の「先富論」の前提的成立要件として、手段の当否および「共富(=全体富裕化)」という全体目標との連関の両者が要請されるにも関わらず、それが等閉視されることに起因する。先の「向銭看」(=利害得失を判断の基礎とする)に「一切」を冠し、すべての判断を利害関係のみに基づく「一切向銭看」による「唯銭一神教」(Money Monotheism)の成立であり、「唯銭一神教」への絶対帰依の結果として、「富」という最終結果のみに焦点が当てられるからである。
そして、第二に、時間的進行と共に生活向上感の相対的低下が挙げられる。「明日の暮らしは今日より良くなる」との向上期待感こそが、経済改革に対する大衆サイドからの支持基盤であったとするならば、眼に見えた形での向上感の低下とは、改革の統合力の低減を直截意味する。換言するならば、それは、改革期における新たな「準拠枠」として選択された「改革イデオロギー」の失効をもたらさずにはおかない。国家体制改革委員会社会調査系統の調査結果では、生活状況の改善テンポは逐年傾向的に落ちてきており、逆に相対的低下を訴える層が増加している。95年段階では、回答者の22%が収入の減少を感じとり、27%が生活水準の低下を訴えている*12。
ただ、その一方で、向上への期待感は依然として強いともいえる。先の国家体制改革委員会社会調査系統の調査によれば、「自己の社会的貢献度ないし周囲の人々と比較しての自らの経済的地位をどのように評価するか」との設問に対し、53.9%が社会的貢献度に比して経済的地位が低いと回答し、周囲との比較でも42.6%が低いと感じている*13。自らの才覚、努力が正当に評価されていないとの認識が傾向的に増加しており、上述した出発点としての不平等による無力感、虚無感をここに読み取ることもできるが、人々は依然として向上期待感を抱き続けていることも確かであろう。
さて、現代中国社会のもう一つの特徴として、私的領域への逃避傾向の可能性が指摘できる。前述の「非政治化(depoliticized)」傾向と共に、個人的価値の相対的重視といってもよい。
第2表は、全国40都市における2000サンプルにより、都市住民の価値意識の分布を問うた結果*14であるが、先ず、「極めて重要」という回答項目に注目して見ると、「幸福な結婚,家庭生活」を「極めて重要」とするものが71.0%と最も高い得点を得ており、それに続くのが「国家の前途」(69.4%)である。すなわち、私的目標としての「幸せな結婚、家庭」と共に「国家の前途」という公的価値の両者がほぼ7割前後と同時に重要視されていることになる。これらに続く回答グループは、「事業の成功」(52.7%)、「豊かな生活」(50.1%)。「個人の才能発揮」(49.5%)の私的領域重視の意識であり、「正義と公衆道徳」(44.6%)、「社会への貢献」(29.9%)、「他者への幇助」(27.5%)等は概して低い。「極めて重要」と「重要」の合計として見ても、「幸せな結婚,家庭生活」(96.4%)、「自らの生活目標の実現」(95.8%)、「国家の前途」(93.2%)、「豊かな生活」(90.9%)と続き、私的価値グループの中に国家という公的関心が嵌め込まれた形となっている。逆に、否定的意識(「あまり重要でない」および「全く重要でない」)では、「暮らしの安定」、「金儲けの仕事」、「社会への貢献」、「他人を助ける」の順に、その重要性が否定されている。そこから浮かび上がる平均像とは、自らの結婚、家庭の幸福を追求すると共に国家の前途にも思いを馳せ、他方で、単なる金儲けのみに躊躇しつつ、社会への貢献、隣人扶助等を旧価値として却け、安定を拒否し、冒険を求めるといった姿かも知れない。ある意味では、各方面に気配りの利いた健全なものともいえなくはないが、前述の“転型期”に特徴的な価値意識の「揺らぎ」現象と見ることもできる。
すなわち、クロス・セクションの分析データが得られないため、定量的に確認することは別作業とならざるを得ないが、暫定的には、これに関して、二つの意味での分極化が措定できる。一つは、個人の私的世界へと沈潜する人々と国家の前途といった公的価値に重きをおこうとする人々との間の具体的グループ間の分岐であり、もう一つの可能性は、同一の個人の内部における私的価値追求と公的価値意識とが未分化のまま混淆して存在する事態である。前者からは、文字通り、“転型期”固有の現象として、旧価値体現者グループに対して、私的領域重視を中心とした新価値グループが発生しつつあることが示唆される。後者は、「引き裂かれた自己」--- 建て前と本音の使い分けと見ることも許されよう。何れにせよ、国家、社会といった公的価値への共鳴は相対的に低調であり、個人、家族の幸福等の私的安寧、幸福の追求といったミクロ世界への沈潜化傾向が読み取れる。中国版マイホーム主義、ミーイズムといってよい。
かつて「砂のような」と形容された中国民衆を統合する原理として制度的に推進されたものが「社会主義」であり、改革期にあっては上からの金儲けの推奨としての「先富論」であったが、今やその「先富論」も当初から先送りされた課題としての格差の顕在化により、歴史的使命を終焉させつつある。再び、中国の民衆は、私的世界へと沈潜し、社会全体としての原子化現象が発生しつつあるのではないだろうか。
第2表 価値意識の分布 (百分比)
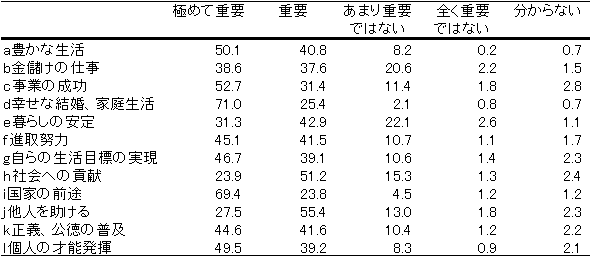
出所:『中国経済時報』1995年7月11日
かくして“中国夢”が今や「見果てぬ夢」と化し、「唯銭一神教」への絶対帰依が進行する情況を、報告者は、かつて「中国病症候群」China Syndromeと名付けたことがある*15。こうした情況に対し、中国側も危機感を募らせつつあり、例えば、邵道生(社会科学院社会学研究所)は「国民心態(mentalit氏j」の危機との観点から、それを「社会心態危機」と呼んで警告を発している*16。邵道生は、現代中国の「国民心態」の消極的部分として、1)物欲化、2)粗俗化、3)冷漠化、4)躁動化の四つの傾向を挙げている。それら四つの傾向も決してそれぞれ独立の事象ではなく、相互に関連しあうものと見られるが、その核心部分たる「物欲化」とは、先に見た拝金主義、享楽主義であり、モノとカネに執着する物神崇拝である。邵は、この物欲化傾向の帰着するところが、倫理と道義の軽視であり、道徳の低下、人格の退化であるとして、社会全体への消極的な影響を懸念している。更に、この「物欲化」の必然的結果として発生するのが「粗俗化」傾向であり、邵は当今の人々の赤裸々な欲望、放蕩そして刺激の単純追求をその特徴として掲げる。「粗俗、庸俗、媚俗、悪俗」なる云いで現代中国版"軽チャー化"傾向を嘆くものといえる。第三の国民心態の危機情況が人間関係の希薄化、冷淡化であり、溺れる者を眼前にして救いの手を差し延べようともしない事例に典型的に見られるようなヒトとヒトの距離の拡大傾向とされている。先に見た価値意識調査でも、「他人を助ける」を最重要視するのは、設問中の最下位グループに属する。最後が「躁動化」であるが、何事にも確信が得られず、苛々と落ち着きがないばかりか、自分が一体何をすべきか確たる目標が得られないといった一種の集団的不安症が客観的に存在すると診断している。
こうした「中国病症候群」を、邵道生は「社会心態危機」として警鐘を鳴らしているわけであるが、邵自身必ずしも充分な対症療法を提起しているわけではない。邵は、ヒトが社会的存在である以上、「社会文化的雰囲気」の制約と影響は不可避だとして、秩序ある規範的なそれを作り出すべきだとして、その際の鍵的事象として教育の重要性、とりわけ「教育者」がかつて担っていた「人格力量」の再構築の必要性を訴えている。
畢竟するに、その他の論者*17も含め、中国側の一般的議論は、改革のより一層の徹底化による社会監督、ないしは市民の覚醒に俟つというものであり、当面する「心態危機」への直接的効果は提示されていない。
従って、その意味では、「中国病症候群」は進行せざるを得ないことになる。当面の即効的対症療法を欠くまま「中国病症候群」が更に進行するならば、どのような事態に逢着することになるのであろうか。取り敢えず、二つの方向性が予感される。一つは、広義の「伝統」への回帰であり、先ずは1950年代--- 「建国の情熱」が中国を覆った時期への懐旧心理--- 「社会主義」伝統への回帰がより一層大きく浮上する。直接体験裡に50年代を知る人々が、今や少なくとも50歳台以上であることを考え併せれば、若者世代をも含めた毛沢東グッズ、「社会主義グッズ」の流行は示唆的である。前述した70年代までの社会主義への幻滅感とこうした懐旧心理とは、社会意識の錯雑なねじれ現象となる。改革敗残者としての「金儲けレース」からの落伍者がこれに加わるならば、ロシアにおける共産党復権にも相似た政治的ムードが形成されることになろう。
また、更に、冒頭で見た“社会転型”概念の背景としての、より大きな歴史的存在たる建国以前の原伝統への回帰もその範疇に含めてよいであろう。中国側が「六害」に数える封建迷信活動、郷村における宗族勢力の蔓延が一つであり、旧来の慣習、組織の再浮上と云う側面でそれを捉え返すこともできる。とりわけ、農村地域における宗族慣習は、基層政権を脅かす動きすらあり、またその一方で、就業、婚姻等の契機として新たな機能を果たしつつある*18。
最後に、もう一つの残された可能性は、文字通りの《神》を新たに求めるものであろう。在来の旧宗教としてのキリスト教信者は、公式資料でも、88年段階で800万人とされていたが、94年では1500万人とほぼ倍増しており、その65%が青年層とされ、宗教活動の一定の自由化政策により、今や「空前の宗教発展期」という*19。更に、泣く宗教としての「咒教」、教祖への絶対帰依を特徴とする「新教」など、さまざまな土着的な宗教集団の存在も報じられており、旧来の枠組を超えた新宗教が跋扈する可能性も排除できないであろう。
- 注 -