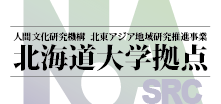2014年11月14日(金)、沖縄県竹富町西表島にある中野地区地域活性化施設(わいわいホール)にて、毎年恒例となっている境界地域研究ネットワークJAPAN(JIBSN)竹富セミナーが境界研究ユニット共催の下で開催された。JIBSNメンバーは多くの境界自治体や境界問題に携わる研究者、実務者から構成されており、今回の竹富セミナーは西表島という空港のない離島での開催だったにもかかわらず、北は稚内、東は根室、西は五島・対馬・与那国の各自治体からの参加があり、日本全国からの研究者・実務者、竹富町の一般市民や地元紙の記者などを含め総勢58名の参加があり、大盛会となった。
セミナーでは、冒頭、川満栄長・竹富町長より歓迎のご挨拶があり、所用により参加できなかった財部能成・対馬市長/JIBSN代表幹事に代わり、小島和美・対馬市役所総合政策部政策企画課長が挨拶文を代読した。そこでは、JIBSNのネットワークを生かして国会に呼びかけてきた国境離島新法の年明けの審議入りの見通しについても説明があった(ただし、セミナー終了後、衆議院解散に向けた動きが本格化し、事態は流動的である)。
セミナーは二部構成からなり、第一部は「日本の国境観光を拓く」と題し、3名による報告が行われた。UBRJでも日本学術振興会実社会プログラム「国境観光:地域を創るボーダースタディーズ」を軸として、中心的に取り組んでいる分野についてである。まず、島田龍(九州経済調査会)により、日本の国境観光のキックオフの役割を果たした対馬・釜山モニターツアーの総括がなされ、現在では花松泰倫(九大・持続可能な社会のための決断科学センター)らと共に、対馬での一泊を含むモニターツアー第二弾が企画されているとの報告があった。また、東京のリタイア層をターゲットにANAセールスとのタッグで、東京→八重山→台湾の国境観光ツアーも企画中とのことである。次に、大浜一郎・八重山経済人会議代表幹事は、石垣市との台湾の交流の歴史を紐解きつつ(石垣市は中華民国蘇澳鎮(すおうちん)と姉妹都市である)、石垣=台北直行便の重要性について力説した。そして、国境観光ツアー実現のために、中華航空をも説得し、夏季のみの季節便を冬期にまで延長することに成功したという。大浜氏は、八重山の自然・治安・公衆衛生のよさに鑑みれば、台湾からの旅行客受け入れのポテンシャルは大きく、国境観光をめぐって民間が主導してしっかり取り組み、行政がバックアップをしてゆくことの重要性を説いた。第一部最後に、高田喜博(北海道国際交流・協力総合センター)が登壇し、国境地域というデメリットをメリットに変え得る、地域振興手段としての国境観光の意義について説明し、現在夏季のみ運行されているハートランドフェリーによる稚内=コルサコフ航路の稚内だけでなく北海道全体にとっての重要性について説明した。右航路は、国境観光というだけでなく、フェリーを利用した経済交流のツールともなっており、2015年を最後に航路廃止の意向が示されていることに遺憾の意が表され、道庁を巻き込んで航路維持を訴えていくべきだと主張した。そして、国境を挟む地域と地域を「広域観光連携」という手法でつなぎ、「国境観光」という統一イメージやブランド化、共通するツールの共同開発などの必要性を力説した。その中で、独バルトキルヒでの「ゲストカード」の試みなどが紹介された。このカードを購入することで様々なサービスを割引きで受けられるといい、このような共通のツールを日本の境界自治体が共同で開発・導入すること可能性を示した。
 第二部は、「日本の国境環境政策を紡ぐ―海岸漂着ごみ対策を中心に―」と題し、2名による報告がなされた。大城正明(NPO法人 南の島々(ふるさと)守り隊)は、西表島の北に位置する小島、鳩間島での漂流発泡スチロールごみのスチレン油への精製についての社会実験の成果について報告をした。現在では、西表島で家庭ごみの中の発泡スチロールを集めて上原港から鳩間島まで運び、スチレン油に精製する広域社会実験も行われているという。新たな島のエネルギー源として期待されているが、NPOや自治体だけでの取り組みには限界があり、グリーンニューディール基金など財政的支援措置の継続の必要性が訴えられた。次に、前述の小島和美・対馬市役所課長が登壇し、平成21年度までは不十分だった海洋ごみ処理に関する国の補助金が、平成22年度以降、グリーンニューディール基金により大幅に増額され、それに伴い、海洋ごみの処理量も大幅に増えたという現状について説明があった。現在、対馬に漂着する海洋ごみの半分は韓国起源で、次が中国起源だという。しかし、岩がちの地形から陸域から海岸に到達して回収できるごみの量は多くなく、過疎化の進展によるマンパワー不足、ごみの量の膨大さ、分別の困難さ、海洋ごみは塩分を含むため処理の難しさなどが指摘された。また、大型焼却施設や最終処分場が島内になく、輸送コストが大きくかさむことが最も大きな問題であるとの紹介がなされ、国の責任でのこれら処理施設の建設の必要性が訴えられた。また、「日韓ビーチクリーンアップ事業」や「日韓海岸清掃フェスタ」の開催など、ごみの出処である韓国をインボルブする努力が既に行われているとのことである。対馬市は、海洋ごみ問題は恒久的な課題であり、行政・市民一体となって取り組んでゆくとのことである。
第二部は、「日本の国境環境政策を紡ぐ―海岸漂着ごみ対策を中心に―」と題し、2名による報告がなされた。大城正明(NPO法人 南の島々(ふるさと)守り隊)は、西表島の北に位置する小島、鳩間島での漂流発泡スチロールごみのスチレン油への精製についての社会実験の成果について報告をした。現在では、西表島で家庭ごみの中の発泡スチロールを集めて上原港から鳩間島まで運び、スチレン油に精製する広域社会実験も行われているという。新たな島のエネルギー源として期待されているが、NPOや自治体だけでの取り組みには限界があり、グリーンニューディール基金など財政的支援措置の継続の必要性が訴えられた。次に、前述の小島和美・対馬市役所課長が登壇し、平成21年度までは不十分だった海洋ごみ処理に関する国の補助金が、平成22年度以降、グリーンニューディール基金により大幅に増額され、それに伴い、海洋ごみの処理量も大幅に増えたという現状について説明があった。現在、対馬に漂着する海洋ごみの半分は韓国起源で、次が中国起源だという。しかし、岩がちの地形から陸域から海岸に到達して回収できるごみの量は多くなく、過疎化の進展によるマンパワー不足、ごみの量の膨大さ、分別の困難さ、海洋ごみは塩分を含むため処理の難しさなどが指摘された。また、大型焼却施設や最終処分場が島内になく、輸送コストが大きくかさむことが最も大きな問題であるとの紹介がなされ、国の責任でのこれら処理施設の建設の必要性が訴えられた。また、「日韓ビーチクリーンアップ事業」や「日韓海岸清掃フェスタ」の開催など、ごみの出処である韓国をインボルブする努力が既に行われているとのことである。対馬市は、海洋ごみ問題は恒久的な課題であり、行政・市民一体となって取り組んでゆくとのことである。今回のセミナーで、国境観光の発展と国内での定着に向けて着々と歩が進められている様子が分かった一方で、海洋漂着ゴミ問題については対策に一定の進展がみられつつも、その限界についても詳らかになった。将来的には、海洋ごみ問題の専門家や国レベルの実務家を交えて、日本のゲートウェイたる国境離島から越境海洋ごみ対策のモデルケースを構築するような取り組みの必要性を感じた。
セミナー後の懇親会では、西表島祖納(そのう)集落の方々による、手作りの島料理と郷土芸能によりもてなされた。また、翌日の西表島巡検を含め、大原港から移動するバス車内では、竹富町役場の勝連松一・企画財政課長より、西表島の歴史と現状、各集落の特長などについてたいへん丁寧なご説明をいただいた。そして、企画財政課の小濱啓由さんにはセミナー組織とロジ統括の労をお取りいただいた。初めて訪れて驚いたのは、西表島や竹富島を含め、観光地化された島々はものすごく元気なことである。今後の竹富町の発展を心より祈念させていただくと共に、今回のJIBSNセミナー成功に向けてご尽力いただいた竹富町の皆さまに心から感謝の言葉を申し上げたい。(文責:地田 徹朗)



 Eurasia Unit for Border Research (Japan)
Eurasia Unit for Border Research (Japan)

![境界地域研究ネットワークJAPAN [JIBSN]](/ubrj/img/com/side/bnr_jibsn.jpg)