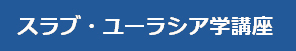 |
| I.大学院教育の特徴 | II.学位 | III.大学院の入学試験 | ||||
| 修士課程(博士前期課程) | 博士課程(博士後期課程) | |||||
| 一般入試 | 外国人留学生特別入試 | 社会人特別入試 | 一般入試 | 社会人特別入試 | ||
| 大学院ニュース | 授業紹介 | 大学院生助成 | 在籍者 研究テーマ一覧 | 学位論文一覧 | 修了者の声 | 問い合わせ先 |
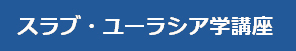 |
| I.大学院教育の特徴 | II.学位 | III.大学院の入学試験 | ||||
| 修士課程(博士前期課程) | 博士課程(博士後期課程) | |||||
| 一般入試 | 外国人留学生特別入試 | 社会人特別入試 | 一般入試 | 社会人特別入試 | ||
| 大学院ニュース | 授業紹介 | 大学院生助成 | 在籍者 研究テーマ一覧 | 学位論文一覧 | 修了者の声 | 問い合わせ先 |
修了者の声 新井洋史(2024年度博士号取得)
社会人院生的「スラ研のすすめ」のような何か
新井洋史
まず、スラ研で学ぶことを検討中の方々を念頭に、総合演習(「金曜ゼミ」)の魅力をお伝えするところからこの小文を始めたいと思います。毎週金曜に行われるこのゼミで、院生は各学期に最低1 回の発表が義務付けられます。その時には、自分の発表に対して他の院生や教員の方々から、厳しくも有意義な質問やコメントをいただくことになります。ただし、これは大学院として当然の営みです。私にとって何より貴重だったのは、他の院生の皆さんの発表です。私は社会人学生として入学しましたが、それまで人文科学系の分野などには全く縁がありませんでした。そんな私にとって、未知のテーマについての研究者の卵の報告は十分迫力がありました。「卵」とはいえ博士後期課程の学生は孵化直前の状態ですから、いわばセミナーや講義を聞いているようなものです。また、続いて行われる質疑応答からも大いに刺激を受けました。鋭い質問に接するたび、「自分もこういう質問ができるようになりたい」と思ったものです。ちなみに、私以前の遠隔地居住の社会人院生の皆さんにとっては、毎週の金曜ゼミに出席することはほぼ不可能でした。私は新型コロナウィルス感染が続く中で入学したので、オンライン開催が定着しており、居住地である新潟にいながら、あるいは出張先から出席することができました。不幸中の幸いというべきか、よい巡りあわせだったと思います。
さて、私が博士(学術)の学位をいただいたのは2025 年3 月です。2021 年4 月に北海道大学文学院博士後期課程に入学しましたが、3 年間では論文を完成させることができませんでした。在学3 年目が終わろうとする時期、私には理論上3 つの選択肢がありました。第1 に、学位取得をあきらめる。第2 は、引き続き在学して学位取得を目指す。第3 は、単位修得退学した上で、学位取得を目指す。このうち第1 の道は論外で、残り2 つのうちどちらにするかを考え、第3 の道を選びました。そうすれば授業料を払わなくてよくなるという実利的な側面もありましたが、なにより「退路を断つ」覚悟をしなければ成就しないだろうと考えたからです。その際に決め手になったのは、「単位修得退学後1 年以内に学位申請論文を提出した学生は、論文審査料を請求せず、論文審査に合格した場合は課程博士として取り扱う」というルールでした。1 年以内に論文を出さなければ、3 年間の在学が無駄になるという状況に自らを追い込んだわけです。今回は、それが奏功して何とか学位をいただくことができました。
「今回は」と書いたのは、文学院に入学したこと自体、自分としては「退路を断った」つもりだったのに、上述の通り3 年では目標を実現できなかったからです。話は飛びますが、私は1990 年に新潟県庁職員として社会人キャリアをスタートしました。その後、新潟県などが設立した「環日本海経済研究所(ERINA)」というシンクタンクへの出向を通じ、徐々に研究の仕事に近づいてきました。それでも当初の仕事は、与えられた課題について調べる「調査」が中心であり、自らテーマを設定して探求を進める「研究」ではありませんでした。しかし、出向先のERINA に転籍したころから、徐々に研究的な仕事が増えてきました。そんな私に対して、当時の西村可明所長、その後任の河合正弘所長は、しきりに博士号取得を促して下さいました。「あなたなら、これまでの業績をきちんとまとめて論文博士の申請をすれば大丈夫」といった心強い励ましのお言葉を何度もいただきました。その都度、「わかりました、頑張ります」と答えるものの、怠け者の性分ゆえ、全く作業が進まないという時期が約10 年にも及びました。この状態に終止符を打つべく決断したのがスラ研に入ることでした。その時は、3 年間という時限を設定して退路を断ったつもりでした。しかしながら、その決断だけでは足りず、最後は「単位修得退学後1 年以内に提出しなければ元の木阿弥になってしまう」という、もう一段強いプレッシャーを自らに課すことで、ようやく目標を達成したことになります。
私の論文タイトルは「北東アジアにおける国際協力を通じた地方振興に関する考察」というものです。30 余年の職業人生を反省しながら論文をまとめ、還暦のタイミングで学位を授かりました。半生の区切りをつけることができた思いです。1990 年代には、東西冷戦終結を受け、環日本海経済圏の実現に向けた様々な取り組みがなされていました。ロシアのことを何も知らないまま、人事課に命じられてハバロフスクでのロシア語研修に赴いたのは、ロシア連邦成立直後の1992 年2 月でした。ERINA が設立されたのは1993 年です。翻って近年は、当時とは全く異なる世界になっています。新潟県庁を辞めて移ったERINAも2023 年3 月に解散してしまいました。(論文執筆が遅れた言い訳として、職場が無くなる、新たな職場に移る、というドタバタの中で落ち着いて研究ができなかったという事情を挙げさせてください。)こうした大きな情勢変化が起こった(起こりつつある)タイミングで、一つの時代を振り返る作業をしたことは、それなりに有意義であり、少なくとも次代の研究者にとっての研究資料を用意することはできたものと考えています。
最後になりますが、この場をお借りして、入学時の指導教員だった田畑伸一郎先生、その後を引き継いでくださった服部倫卓先生をはじめとするスラ研の先生方、お世話をいただいた職員の皆様、そして「金曜ゼミ」でともに奮闘した院生の皆さんに感謝申し上げます。
以上、個人的なことばかりを書き連ねましたが、このような私の経験を励みにして、スラ研での学びに向かって一歩踏み出す方がおられれば、望外の幸いです。
(2025年3月)
[修了者の声index]
- 新井洋史(2024年度博士号取得)
- 山田愛実(2023年度修士課程修了)
- ベクトゥルスノフ・ミルラン(2022年度博士号取得)
- 生熊源一(2020年度博士課程修了)
- 大武由紀子(2018年度博士号取得)
- 谷原光昭(2018年度修士課程修了)
- 秋月準也(2017年度博士課程単位取得退学)
- 服部倫卓(2017年度博士課程修了)
- 長友謙治(2016年度博士課程修了)
- 植松正明(2015年度修士課程修了)
- 真弓浩明(2015年度修士課程修了)
- 井上岳彦(2014年度博士号取得)
- 斎藤祥平(2014年度博士課程修了)
- 野口健太(2011年度修士課程修了)
- 石黒太祐(2011年度修士課程修了)
- 宮風耕治(2010年度修士課程修了)
- 麻田雅文(2010年度博士課程修了)
- 高橋慎明(2009年度修士課程修了)
- 秋山 徹(2009年度博士課程修了)
- 『修了者の声』一覧へ戻る