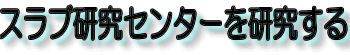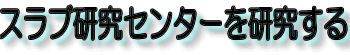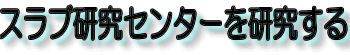
1996年点検評価(抜粋)
セ
ンターへの評価と提言(2)
木村 崇(京都大学)
「小さく生んで大きく育てる」というのは子育てのこつだが、人間の営む創造的な行為のすべてに通ずる道理でもあるようだ。スラブ研究センター創立40周
年記念の行事に参加して、草創期から中期へかけて活躍された方々のお話を聞いて、あらためてそのことを思い知らされた。
小さいまま育ちきらないこともある。大きく生まれても立派に成長する保証はない。スラブ研究センターが着実に前進しているのには、それ相当の理由がある
にちがいない。一般的には、優秀なスタッフと研究活動資金が必要にして十分なだけ保証されてい、理にかなった研究体制と支援体制が確立しており、それらを
しっかり包み込むゆったりした施設があれば、研究機関としての成長は順調に進むはずである。誰の目にも明らかなように、センターの歴史は、少数ながら優秀
なスタッフがいたという要因を除けば、あらゆる不足との不断の格闘の歴史であったし、ここ当分は、あるであろう。その負の諸要因を乗り越えて、今日セン
ターが国内だけでなく世界的にも高い評価を得られるにいたったのは、研究の領域と研究支援領域の両方で、少数ながら優秀なスタッフが八面六臂の活躍をして
いるからである。
センターの一人一人が、研究・行政・組織運営のあらゆる面にわたって支出している労力は、同様の研究活動をしている他の組織とくらべて、何倍にもなるは
ずである。そのことについて私たち外部の関係者は深い敬意と感謝の念を抱いているが、このままではいけないとも考えてる。自己犠牲が日常化しているところ
では長い期間を経るにつれ、投下された労力の量にたいして、得られる成果がしだいに比率を低めて行くのは目に見えているからである。点検評価の視点として
は、まず第一にこの矛盾をどう克服するかという点に据えられるべきであろう。「限りなき献身」の時代はそろそろおわりにすべきだ。この問題については、内
部の方々の自己評価の中にも多少触れられているが、具体的展望が切り開かれているようには見えない。
スラブ研究センターの現状を点検評価するための第二の視点は、伝統をいかに受け継ぎ、発展させるかという点だろうと思う。私が言う伝統とはなによりもま
ず、これも40周年記念のときに聞いて感心したことなのだが、センターの内部における合意形成プロセスの丁寧さである。これはある意味では「小さい」こと
の効用でもあった。これから部門が増えそれぞれの部門の活動範囲が広がっていけば、合意形成の手続きはおのずから簡略化されて行かざるをえないであろう。
私はかなり大規模な機関に所属しているので日頃痛感しているのだが、「生身の」組織には適正規模というものがあるように思われる。センターのばあい、紀元
二千年までの将来像の範囲でなら、今のような丁寧さでやっていけるであろう。しかし部門が増えていけば、センターにもっとも期待されている、学際化された
研究というものをいかに具体的に組織するかという課題は、加速度的に困難になって行くのは必至であり、今から対策が用意されているべきである。スラブ研究
センターが今日あるのは、丁寧な合意形成という伝統のおかげだと思われるので、その創造的発展形態が考え出されるように期待したい。
点検評価の第三として考えられるのは、内外のスラブ学学界の諸分野との連携の現状がどうなっており、今後どのように進められて行くべきかという視点であ
ろう。センターはそれ自体が自己完結した研究機関であると同時に、わが国におけるスラブ学全体の統括的組織者としての機能も期待されている。センターが順
調に発展してきたのは、イデオロギー対立の激しかった冷戦の時代から一貫して、そのような対立を超越した、「みんなの」スラブ研究センターというものは本
当に必要だという価値観がすべての研究者の心の中にあり、それによって支えられてきたおかげなのである。たしかに知的連携の面でセンターがこれまでしてき
た仕事は立派である。しかし科研費重点領域研究が始まってまったく新しい局面に入った結果、科研費が終わったあと、この充実した連携の成果をどう受け継い
でいくかという、さらにきつい課題が待ち受けていることも考慮しておく必要があるだろう。こういった視点に立って、4項目についてスラブ研究センターを私
なりに研究してみたい。
a. 前回とくらべ何が前進したか
何よりもCOEプログラムの導入と、科研費重点領域研究の開始が大
きい。
前者については、ある意味ではセンター史上画期的な出来事といえる。現実をよく知っている者として、国立の高等教育機関や研究所で、どんなかたちにせよ実
質的に定員が増えるのは、ご同慶のいたりである。スラブ研究センターには、他のCOEよりも分母が小さい分だけ利用価値が高いと思われる。とくに、研究者
としての第一歩を踏み出したばかりの人たちがこれによってセンターで体験できることは何にも代えがたいくらい大きな意味を持つはずである。かねがね、セン
ターの助手ポストがきわめて少ないのは問題が多いと思っていた。文部省や大蔵省には、文系の助手が、後継者養成、あるいは「研究文化」の継承という意味で
どれほど大切かということの認識が希薄なようである。その意味でも今後このポストを、さすがスラ研といわれるように活用していただきたい。若手研究者の養
成の面では、たしかに自前の院生を持つことも必要だが、センターのネットワークに、全国にいるあらゆる分野の、大きな可能性を持った若手研究者が捕捉され
ていて、たとえば鈴川基金を何らかの手当を講じてさらに拡大
し、定期
的に実習的訓練を体験させることによって自立できるきっかけを提供するというようなプロジェクトも重要ではないだろうか。
科研費重点領域については、「金の切れ目が縁の切れ目」にならない
ように
するにはどうすればよいかが次の大きな問題になる。そうしないためには、今形成されている各研究グループの有機的なつながりをできるかぎり崩さずに、それ
ぞれが今後も科研費やその他の補助金を獲得しながら、センターの実施するプロジェクト研究計画に参画していただくような方策も考える必要があるように思
う。
b. 川端提言はどう生かされたか
センターが準備している点検報告書第2号の案を読むかぎり、どうも1号に載った外部評価に対して、その後どういう努力がなされたかについては、直接の言
及がないように思われる。川端さんはこれからのセンタースタッフが専門化と総合化との関係をどう発展させていくかについてすこし危惧されていたが、それは
大丈夫なのだろうか。おそらく川端さんのご指摘は、私も共同研究員としてかかわっている文学の分野から見たとき、今のセンターの動向には専門化の方向が強
まる一方で、学際的な共同研究の可能性の追求が希薄になってきているのを心配されているのだと思う。草創期には合宿で、経済や政治や歴史の方も熱心に文学
論議に加わっていたらしいが、たしかに今はそのような光景は見られない。これは文学者の側にも責任がある。自分たちだけの学会で取り上げるような問題をそ
のまま持ち込んでいるために、非専門の人たちに門戸を閉ざしているきらいがないでもないからである。今こそ本当は文学も歴史も、政治も経済も学際的に関わ
らなければならないような問題が潜在的に提起されているはずなのにである。
アジアへの視点という問題提起もしかりである。たとえば最近なくなった司馬遼太郎の発言には、私の専門からすれば色々問題が多いけれど、個別の学会を越
えたアプローチが必要な問題があったことは確かだ。センターの運営が部門中心になればなるだけ、このような要請に対する反応が鈍くなっていくのは必然であ
る。そうならないようにするためには、専門を特定しない部門を置く必要があるかも知れない。
c. 西村提言はどう生かされたか
点検報告書第一号の西村さんの指摘には、さらにつっこんだ問題提起があった。
彼は、「総合研究にはスタッフが単に個人レベルで参加するものなのか、それとも部門を単位として参加していくのかという問題がある。このような疑問が生じ
るのは、現在五大部門が設置されているが、部門の専門分野と当該部門所属スタッフの専門分野とがかならずしも照応していない場合があるからである」とい
う。私は、そのような一種の「腸捻転」は、学際的な研究テーマを追求する際には、人事採用の計画との間にタイムラグが生じるので、あるていど避けられない
とは思うし、研究というものがまず第一に個人の内発性に依拠している以上、いたしかたのない面もあるとは思う。しかし、これは西村さんが言うように、現在
のスタッフの固有の専門分野分布が「学際的総合的研究」の「発展の初期段階」においてそのようであるということはさておき、いつまでも固定されるべきでは
ないだろう。センターの将来計画には、文字どおり学際的な研究体制を確立するために、個々のスタッフが、あくまでも研究の内発性を堅持しつつ、それぞれい
かに「変身」していかなければならないかについて、研究内容にかかわる中・長期計画が練られる必要があるということだと思われる。
d. 文字どおり中心となるために
わが国の研究環境の貧困な状況が劇的に好転するとは考えられない。一方スラブ学学界のさまざまな分野において、解明が求められる研究テーマが今後ますま
す増えていくことは、避けられない。ところが私の所属する大学の範囲で見る限り、学生がスラブ圏の諸問題によせる関心は、ますます先細って行くようなもど
かしさ、はかなさを感じずにはおれない。わが国のスラブ関係の学問は個別の大学では、おしなべて「少数民族」の立場に置かれていると思われる。しかし、小
さな力も、中心があって、そこに結集していれば、それなりの力になるはずである。中心があれば数少ない若手の研究者も意を強くするであろう。私自身がスラ
ブ研究センターに望むのは、そのような「希望の星」的中心になってほしいということである。また一方、これは既存のスラブ関係諸学会の、単なる寄り合いの
場であってはならないと思う。個別学会で行われている研究と、スラブ研究センターが組織する研究は、どこかで違っていなければならないと思う。その独自の
研究テーマを設定できるかどうかが、本当にセンターになれるかどうかの分かれ目になるような気がする。